私はゲームアートのアウトソーシング事業のほか、専門学校の非常勤講師としても活動しています。ここでは、講師として取り組んでいる授業の内容や、その考え方を共有したいと思います。学生たちの成長を支えるこの仕事は、私自身の学びの場でもあり、日々やりがいを感じています。
きっかけと想い
所属先の専門学校は、私がかつて通っていた母校です。活動を始めたのは2022年、私が独立したタイミングで、当時の担任の先生からお誘いを受けたことがきっかけでした。
私がゲームアーティストとしてのキャリアを歩めているのは、この専門学校での学びがあったからにほかありません。今度は恩返しをしたいという思いと、未来のクリエイターの成長に貢献できる仕事にやりがいを持って取り組めるという期待がありました。この役割を通じて、学生たちに夢を与え、導く喜びを実感しています。
授業の構成
ゲーム企業への就職を目指す学生を対象に、キャラクターデザインやコンセプトアート、UI/UXデザインを題材とした授業を展開しています。形態としては、講義と実習を織り交ぜたものになっています。
講義では、デザインやアート制作に必要な知識、技法の解説や、ゲーム産業に関する情報、就職活動のためのアドバイスなどを、自分の経験と共に伝えています。実習では、基礎画力を向上するためのデジタルスケッチや、実際のゲーム開発を想定したデザイン制作などを提供しています。また、学生が制作した作品に対する添削や講評も取り入れ、個別の成長をサポートしています。
多様な学生に適した授業設計
専門学校は入学試験がないため、多様な学生が入学します。例えば全くイラストを描いたことがない生徒もいれば、すでにフリーランスとして仕事を請け負っている生徒もいます。また、皆それぞれ好きなゲームやアートスタイルが違うため、目指す進路も異なります。それらが一つのクラスとして一緒に授業を受けるのです。こういった環境では、全員を同じレールで学ばせるスタイルだと、満足度にムラが出てしまいます。そこで、私の授業では、全ての学生が限りなく高い満足度を得られるよう、カリキュラムを工夫しています。
- 講義による基礎知識の共有: 初学者向けの基礎知識から、プロが実践している技法まで幅広い内容を共有します。流行りの技法や情報は食いつきが良いですが、付け焼き刃で廃れやすいもの。ですから、ここではどの学生にも知ってほしい普遍的な内容を伝えています。時代を超えて役立つ基盤を築くことが、長期的な成長につながると信じています。
- 即戦力を見据えた実践課題: 学生に取り組んでもらう実習は、開発現場で実際に直面するような内容にしています。必然的に難易度は上がり、負担は大きくなりますが、将来を見据えた最短ルートだと考えています。「習うより慣れろ」の精神は、ゲームクリエイターの世界でも通用します。
- マンツーマンの添削指導: 学生が制作した作品に対する添削や講評を、リアルタイムで直接対話しながら行います。現代はSNSをはじめとしたインターネットで知識や情報を簡単に収集できますが、自分自身に最適化されたフィードバックを得る機会は少ないものです。だからこそ、この指導は非常に喜ばれます。学生の反応を確認しつつ丁寧に進め、本人がぶつかっていた壁や課題を解消します。作品が見違えるように良くなっていく様子を見ると、とても嬉しそうにしてくれます。このような反応をもらうことは、私にとっても大きな喜びです。こうした個別対応が、多様な学生の満足度を高める鍵となっています。
学生との向き合い方
多様性が重視される昨今、技術の伝え方や指導の姿勢にはより繊細に気を配る必要があります。多様な考え方が全世界で共有されるようになり、正解が一つではなくなった今、より柔軟に受け入れ、尊重する姿勢が求められます。
自分の経験から得た知見や普遍的な法則は、確信を持って伝えつつ、新しい価値観や個別の思想は柔軟に受け入れる度量を心がけています。ゲーム産業でも、プレイ人口の増加に伴い、アクセシビリティが年々充実してきています。私の授業でも、こうした視点を重視します。トレンドの移り変わりが早い業界なので、自分の固定観念に縛られることは大きなリスクです。講師として技術や知識を指導する立場ですが、学生との関わりから得られる学びや気づきを大切にすることで、良好な関係を築き、自身の成長にもつなげています。
進路相談で伝えること
進級して就職活動が近づくと、多くの学生は進路やキャリア設計の悩みにぶつかります。企業説明会や進路相談会、キャリアアドバイザー、そしてSNSなどから、あらゆる角度からの情報や意見に晒され、方向性を見失うケースは少なくありません。
例えば、「この分野での就職は厳しい」「今の君では実力が足りない」といったネガティブな意見です。これは一見、真実を語っているように思えますが、そこには何の責任も根拠もなく、ただその語り手の先入観やポジショントークにすぎないケースがほとんどだと感じています。
私がこうした悩みに直面している学生たちに伝えていることは、「周りに流されず、自分が実現したい未来を自分で掴み取ろう」ということです。自分が無理だと思えば何も成し遂げられません。人の意見に頼って導き出した決断は、問題の先送りでしかなく、いずれ大きな後悔として跳ね返ってきます。いずれにしても、自分の力で道を切り開かなければならない時は訪れるので、それであれば若く可能性に恵まれた時期にこそ、奮起して自分の成し遂げたいことに向かって勇気を持って進むことが重要です。
最後に
講師として学生たちに伝えていることは、私自身のキャリア設計や経営方針にも当てはまるものであり、生徒に伝えるのと同時に、自分自身にも言い聞かせている側面があります。学生の未来を応援し支えると同時に、自分自身が模範的な学び手であるよう努めています。この姿勢が、サービス品質を高め、クライアントの信頼につながっていると感じます。
PICK UP
-

教育機関とゲーム産業のズレ
ゲーム業界と教育現場の間には、依然として大きなミスマッチが存在します。この記事では、IGDAの調査をはじめとした信頼できるデータを基に、その現状と原因を分析し、具体的な改善策を提案します。教育の質向上を通じて、業界全体の好循環を生み出す可能性を探ります。 深刻なミスマッチの現状 開発現場ではしばしば、学校で教えられている… -


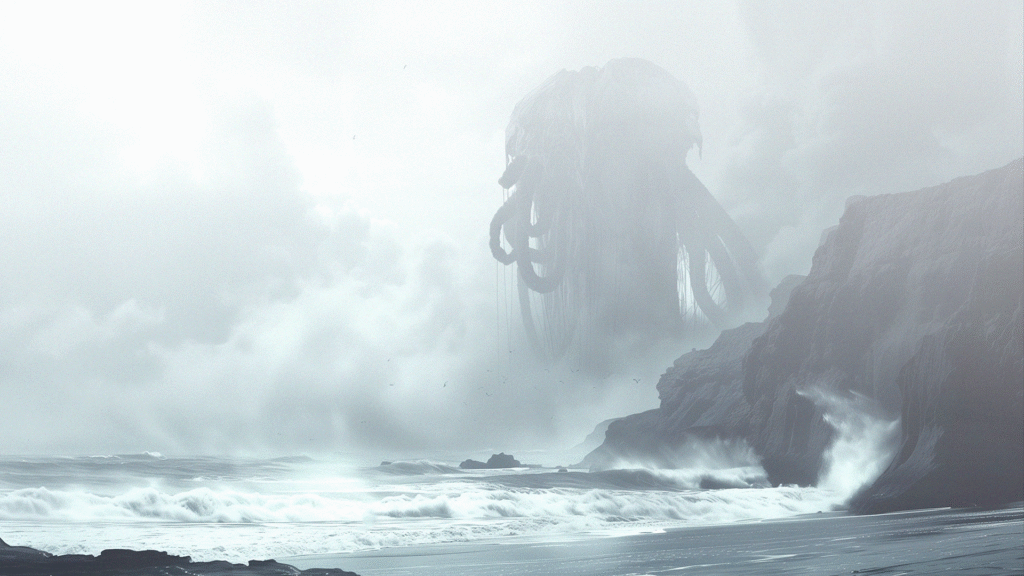
レイスアーツの価値提供と未来への展望
レイスアーツは、日本に拠点を置くゲームアートのアウトソーシングスタジオです。主にゲーム開発者向けに2Dアートを制作し、様々なプロジェクトに貢献しています。アーティストとしての制作経験と、教育者としての指導ノウハウを循環させることで、より質の高いサービスを目指しています。ここでは、弊社のサービス内容と今後の展望について… -


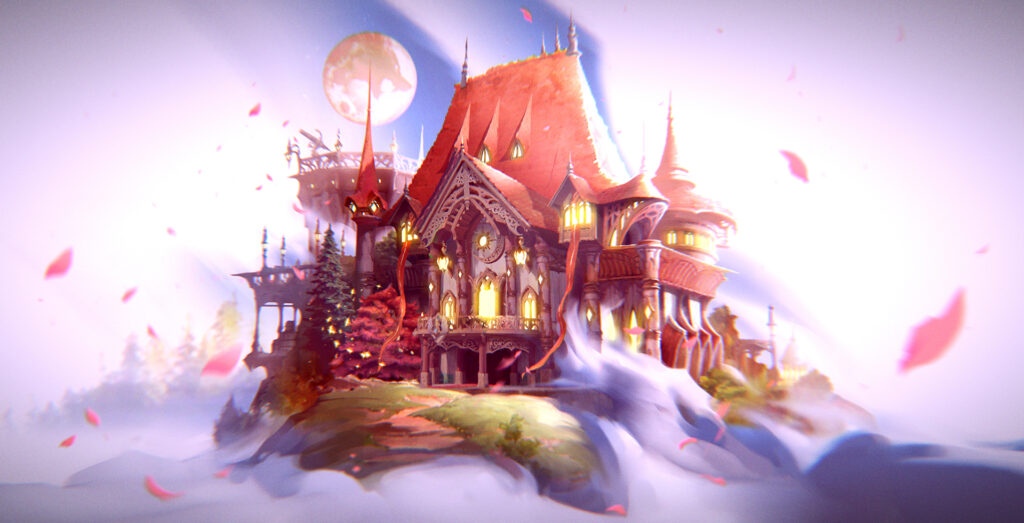
2025年モバイルゲーム業界のユーザー獲得と収益化戦略
ここでは、モバイルゲームのユーザー獲得トレンド、クリエイティブの進化、収益化手法、ソフトローンチのベストプラクティス、AI活用についての知見を共有します。 ユーザー獲得のチャネル多様化と最適化 モバイルゲームのユーザー獲得では、従来の広告プラットフォームを超えた多様なチャネルの活用が進んでいます。現在、ソーシャルメディ…
CONTACT
ご覧いただき、ありがとうございました。レイスアーツは、ゲームの魅力が際立つアートをご提供し、プレイヤーの心を動かすゲームづくりに貢献します。ご相談やご質問などありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。


会社概要
| 会社名 | 株式会社レイスアーツ WRAITH ARTS Inc. |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階 #7F N&E BLD. 1-12-4 Ginza, Chuo-ku, Tokyo-to 104-0061 |
| info@wraitharts.co.jp | |
| Web | https://wraitharts.co.jp |
| 代表者 | 山崎直輝 |
| 主事業 | ゲーム開発 / 教育学習支援 |
| 資本金 | 3,000,000円 |
| 設立年 | 2024年 |
Follow us on

